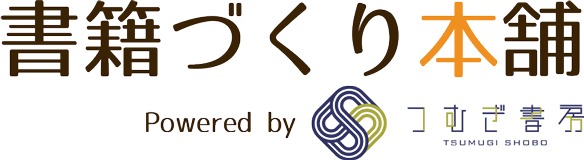当記事では、ブックマーケティング(出版を用いたマーケティング)の意味から基礎基本、具体的な手法、効果を高める上でのポイントまで一連の情報をまとめています。
ブックマーケティングは施策の選択肢になるか悩まれている方は参考にしてください。
ブックマーケティングとは?
ブックマーケティングとは、書籍を広義のマーケティングに用いること、またはその手法を言います。広義のマーケティングは、商品の販売や見込み顧客のリード獲得と言った短期的な売上成果に限定せず、インナーブランディングやアウターブランディング、市場啓蒙といった役割を含みます。
ややこれだけでは小難しいので、次の挙げる目的のため、本を出版することだと理解いただければおおよそ正しいです。
ブックマーケティングの目的
いくつかの目的を持つケースが多いこと、複数の効果が同時発生しやすいことから、きれいに分類することが難しいです。網羅的に説明したいため、多少の要素重複を無視して紹介します。
企業や製品の認知度を高めるため
やや相性が悪い目的ですが、認知獲得が挙げられます。
書籍そのものが売れると、書店のランキングやSNSでのシェアなどで広がりやすい特徴があります。ただ、マス広告等と比較した際、リーチが限定的で、深い情報を届けられる特性上、認知を狙いにするケースは少ないです。
特定領域の専門性を説明するため
ある程度テーマを絞り込むと、類書がないケースや類書が数タイトルのケースはまだまだ多いです。このため、日本で唯一◯◯をテーマにした書籍の著者である、といった専門性アピールと相性が良いです。
特定領域の権威性を獲得するため
前項とやや重なる部分が多いですが、書籍テーマの領域における権威であることをアピールすることと相性が良いです。
「本を出している先生」という考え方は、まだまだビジネスの現場ではあるでしょう。著書を持つと、Google検索等で「著者」として取り扱われる場合もありますし、Wikipedia等でまとめられることもあります。
曖昧な部分ですが、セミナー講師の顔写真横に書影が並んでいると「なんか凄そう」と感じたことがあるのではないでしょうか?
特定市場を啓蒙するため
競合製品がなく、新しい市場を作り出すタイミングや代替製品として市場を切り開いていく場合に、書籍を用いることがあります。
順序立てて説明すれば、関心を持つ方々が多いはずだが、ターゲットユーザー層は自社商品を想起しないケース(ソリューションとして想起しないケース)で、市場を作り出す役割です。その業界のリーダーが取り組むケースが大半です。
※市場拡大のうまみを最も受けるのがリーダーであるため。
書店という場から見込み顧客に接触するため
検索広告を活用し十二分にプロモーションしている。ディスプレイ広告、動画広告、タクシー広告、展示会などなど、幅広い媒体・チャネルに投資してきた先に残る、Amazon広告や書店というチャネルを求めて出版するケースです。
雑誌の見開き広告は広くリーチするには相性が良いですが、行動を変える力は弱いことから、製品によっては1冊の書籍を選択する場合があります。
コンテンツの二次利用のため
出版社との契約種類により、出来るできないが分かれますが、書籍原稿を社内資料や社外配布用のホワイトペーパー等に二次利用するケースです。
千数百円で販売されている書籍のサマリーPDFが無料で配られていれば、魅力的に見えるケースもあるでしょう。まとまった情報になる利点やCVRを上げる、CPAを下げるといった狙いはあります。
自社従業員の教育に活用するため
経営理念や取り組む領域のビジョンなどの理解度を高める目的で出版するケースです。浸透を図る、人材育成を効率的にするといった狙いや効果を目指す場合です。
就活生等に自社考えを伝達するため
前項と近しい内容で、未来の従業員に読んでもらうことを目的にしたケースです。
企業理解が深い人材を採用できるメリットで、選考の効率化にも寄与します。企業が成し遂げたい社会の未来像を示すことで、目指す先に共感した人材を吸い寄せる狙いがあります。
ブックマーケティングのメリット、デメリット
一部前述の目的と重なる部分もあるため、スリムにまとめようと思います。
メリット
書籍は薄いものでも120ページほど(5万文字~)ボリュームのあるものでは、400ページ超(20万文字~)と圧倒的な情報量を伝達できます。
一般的な広告プロモーションと比較し、紙という保存性から長い期間効果が続くことも挙げられます。
他に、書店というチャネルのお話や二次利用のお話は先の通りです。
一般的な広告と違い、見せ方によっては講演依頼やメディア出演依頼などに繋がりやすい点も言えるでしょう。
デメリット
いくつかあるうち、PDCAが回らないことは挙げておきたいと思います。デジタル広告と異なり、数字での確認がしづらく、効果範囲も不明瞭です。書店の売上情報は発売から半年程度経過しないと見えてこない点は最たる例です。(POPレジデータから分かる範囲での集計など工夫のしようはありますが、売上冊数の確認に半年かかる訳です。)表紙だけ変えたABテストは当然NGです。
情報量が多い話をメリットでしました。裏を返せば、情報作成コスト(時間なり、費用なり)も大きくなります。紙の特性上、一度世に出た書籍を修正することはできませんから、Web記事と比較しても校正を入念に行うことが求められます。
最後に比較先次第ですが、コストの視点ではないでしょうか。テレビCM等に比較すれば安価ですが、最低限かかるコストが一定額あるため、Web広告等と比較すると手が出しづらいと言えるでしょう。何より、プロモーションを目的にしている場合、まずはWeb広告をある程度実施し、プラスアルファで検討すべきがブックマーケティングだと思います。
ブックマーケティングと企業出版、自費出版との違い
冒頭での説明の通り、ブックマーケティングは書籍を用いたマーケティングです。企業出版や自費出版は、出版する著者(企業)が費用負担する出版形態を意味するもので、ブックマーケティングを実行に移す際の具体的な代行サービス名です。
あなたの会社がブックマーケティングに取り組むことを決めた場合、内容を練ることは社内で完結できるかもしれません。デザイン、印刷製本、流通、保管などの機能を社内に取り揃えている企業は滅多にないでしょうから、デザイン会社や印刷会社、取次や倉庫会社に委託をする訳です。(実際にところ、1タイトル発売だけの計画では取次店や書籍用倉庫会社は契約をしません。)
商業出版でブックマーケティング?
商業出版は、出版社が費用負担し出版する形態です。出版社の目的は利益を上げることです。商売ですから当然です。
ブックマーケティングの目的は、大半の場合で書籍売上(伴って利益)ではないため、目的がズレることから実現しにくいと言えます。
ただ、昔からの商習慣で買い取りをつけ、企画内容の折り合いをつけて出版に至るケースもあります。具体的には、製品パンフレットのような宣伝に寄りすぎず、読者が持ち帰るもののある企画とし、初版4,000部のうち2,000部を著者(会社)が買い取るという内容です。
ブックマーケティングの手順
1.目的を定める
当記事の目的に関するブロックでも主要なものを紹介しました。目的を書き出し、優先順位を決めます。できれば一人で考えず、社内の複数名で考えると良いでしょう。多くの企業は企業のさらなる繁栄や継続的な繁栄を願っているはずです。そのために、自社が強化すべき点がどこか、強化されるとどういった変化が起きそうか、の視点で意見を出し合ってみます。
後ほど、再度スタートに戻るプロセスがあるため、悩みすぎずに次のステップに進めることも大切です。
2.ターゲット読者層を定める
次にどういった方々に届けたい書籍なのか、これを考えます。
箇条書きにすることも一つですが、後の工程を考えたい際に、円を重ねていく方法をおすすめします。一般的には使われない例になりますが、メインが東京都、その上に関東、その上に本州と3つの円を重ねます。
円が重ならないケースもあり得ます。1つ目の円が社内従業員の若手層、2つ目が現在就職活動をしている大学生といった具合です。
3.部数と効果のバランスを定める
伝えたいことと売れる要素のバランスを定める工程です。ターゲット層を絞りに絞って言葉を選べば、分かりやすくて響く内容になるでしょう。一方でターゲットから外れた人にとっては、読む価値を感じられない一冊になります。
多く売れる(部数)を選ぶほど、世の関心が高いテーマを幅広い人に理解・共感してもらえる企画にする必要があります。
万人受けする企画にするほど、自社独自の主張は薄まりやすく、得たい効果も低減しやすいです。(必ずそうかと言われたら両立するケースもありますが、多くは相反するものとお考えください。)
リーチを伸ばし影響力を下げるか、リーチを限定し影響力を高めるかの二項対立の中で、どのあたりに調整するかの工程です。
4.企画、目次案をまとめる
仮の書名、概要、目次案を作成します。書店での立ち読みを意識する場合には、冒頭に関心を引けるコンテンツを配置すると良いでしょう。順序立てて、分かりやすい流れにすることは王道ですが、読み手を選ぶ点を理解しましょう。
書名の付け方、目次案のまとめ方を解説すると本題からズレるため、また別の記事で紹介できればと思います。
5.プロモーション、営業の仮計画を作る
書籍の宣伝、営業について計画を立てましょう。
一般的なチャネルとしては、Web広告(検索、Amazon、SNS、動画)、新聞・雑誌広告、電車広告をおさえましょう。
次にインフルエンサーや書評、口コミの経路です。そして最重要となる、書店店頭や書店の売上ランキングです。
書店で大きく陳列されると売上が伸び、売上が伸びるとランキングに掲載され、さらなる購入を促進します。書店に十分な数を仕入れてもらうには営業が必要です。営業成績は書籍のテーマ、タイトル、定価に加え、広告の予定やメディア露出の影響を受けます。
大型書店で面陳列してもらい、ランキング1位をとりたいといったご相談はよくいただきます。表立ってかけないこともあるため、準備と進め方で気になる点があれば、お問い合わせください。
6.先頭1に戻り、1~3の実現性を検討・再考する
ここまでの整理が進むと、難易度の高さや費用負担が予算と合わないなど、課題が見えてくるケースがあります。
目的を欲張りすぎていた場合やターゲットを絞り込みすぎていた場合などもあるでしょう。
ここで課題を放置せず、適切な設定に直すことが大切です。
7.検討結果次第で、4.5を調整する
同様に、具体案・プロモーション案を修正します。お話を伺う中で多いのは、新聞広告などを計画から外し、地道な知人への書評依頼や献本、書店営業やPOP等への注力です。
プレスリリースを打たれるケースもありますが、商品発売のプレスリリースになるため、媒体に取り上げてもらうことは期待しづらいです。
8.執筆、編集をする
企画がまとまれば、実際に原稿執筆・編集・校正の工程に進みます。
ご自身や社内で原稿を作成される場合もあれば、企画段階からライターを入れて作成されるケースもあります。どうしてもライターを入れるとコストが高額になるため、自社内で作成されることが多いでしょう。
9.本文レイアウトデザイン、装丁デザインを作る
原稿がまとまると、本文ページのレイアウトデザインを作成し、レイアウトに沿って本文ページの印刷データを作成していきます。
一旦の完成となれば、PDFで校正する場合もあれば、ゲラ刷りして確認する場合もあります。本文データが出来上がると、ページが決まることで背幅が決まります。表紙・カバー・帯のデザインデータ作成へ進めていきます。
しおりやスリップ(売上カード)を付ける場合は、この工程で合わせて準備します。
10.プロモーション計画、営業計画、広報計画を作る
改めて広告出稿先の枠を抑えたり、広告クリエイティブを作成したりと準備を進めます。Amazonや楽天ブックス等で予約を受けられるスケジュールで計画を立てることが大切です。同時に書店営業の開始時期、著者講演会やセミナーを企画する場合には会場予約もこの時期には完了させます。(500名を超える規模の会場を予約する場合には、より早い時期で手配をします。)
11.印刷、製本する
本を作る工程です。通常は出版社が外部業者に委託する工程であるため、著者自身が何か対応することはないでしょう。(簡易校正・本機校正もこの工程です。)
書籍の印刷や製本には繁忙期があり、(具体的には毎年2~3月)該当時期にあたる場合には、入稿遅延が発生すると大幅な納品日ズレが発生します。スケジュールに注意しましょう。
12.流通、販売の準備をする
完成した書籍は、倉庫に運び込まれます。著者としては発売前に実物を確認したいところかと思います。このタイミングで完成品を受け取りましょう。
流通を担う出版社は、取次店に見本だしを行います。完成品を取次店に渡し仕入れの参考にしてもらいます。
その上で、委託配本・注文配本の希望を取次店へ伝えます。書店営業の結果、獲得した注文分は通常希望通りに配られます。委託配本は昨今の返本率軽減施策の影響もあり、希望が叶わない場合もあります。(注文獲得数が非常に少なく、委託数が多い場合では、より発生します。)
13.プロモーション等を実行する
計画に則り、入稿を進めます。予約数が堅調で増刷が早期に決まった場合など、プロモーション計画を土壇場で修正することもあります。
14.販売開始、効果測定
書店に並び、ネット書店からは発送が始まります。書店様にご挨拶に伺うことやランキング結果を確認する、ネット書店の販売数速報値を確認するなどがこの工程です。
ブックマーケティングの効果を高める方法
各社状況も違えば、目的も違うため、一律の成功法則とは言いづらいですが、主要な点をまとめています。
ターゲットと顧客層にズレがないよう設定する
本の想定読者と事業の想定顧客層がズレないようにすることが大前提です。
(社内向けであれば、そのように読み替えてください。)
ゴールへのルートを漏れなく設計する
本は本で完結させる必要がありますが、目的に合わせて本からの次ステップを設計することが重要です。
コンサル系企業であれば、メルマガへの導線や追加資料のダウンロードを促すことは一例です。書店で本を手に取ったところから、バイネームで会話ができる状態、商談ができる状態への道が繋がっているか確認しましょう。
書店での展開を計画する、実行時にWebでも利用する
ブックマーケティングだからこそのチャネル、書店を十分に活用しましょう。大きく展開いただき、しっかり売ってランキングを目指します。書店で展開する姿を写真に撮る、ランキングに入った際にも写真に撮る。これら情報を現地にいない人にも届けるため、Webを活用しましょう。
Amazon広告に予算をかける
こちらもブックマーケティングならではの、Amazon広告に注力します。
GoogleやYahoo!の広告と比較しても、安価でかつ買い物中のお客様にリーチできます。初速で高評価の口コミが積み上がることが理想です。電子書籍とセットで展開する等も有効でしょう。
著者セミナーの企画、Web広告での集客をする
読者向けの企画だけでなく、広く展開するセミナーを企画すると良いでしょう。
無料で、誰でも、オンラインでどこからでも、参加できるような仕組みが有効です。買って読むほどではないけど興味を持ったユーザーを取りこぼさない受け皿にもなります。
ブックマーケティングの標準的な費用
ここではブックマーケティングの費用を4つに分類し整理しようと思います。
- 企画費
- 執筆費
- デザイン、印刷製本、流通費
- 広告宣伝費
それぞれの費用の説明、相場感、価格幅の理由を確認しましょう。
企画費
当記事でも触れてきた目的、ターゲット、企画概要、プロモーションや営業計画をまとめる作業費用です。
無料で提供するところから、20万~50万円程度の費用を定めている会社が多いでしょう。
無料や安価な会社は、著者側で目的整理を主導いただくケースが多いです。企画作りやプロモーション計画は実行コストに企画費用を含めているケースもあります。
執筆費
書籍の原稿を著者に代わって執筆する費用です。
10万文字程度の原稿で、20万~100万円程度と幅があります。インタビュー等をベースにする場合は、取材費や交通費等の名目でプラスαかかる場合があります。
執筆はほぼライターの技術力に応じて価格が上がります。(出版社内の社員が執筆するケースは少ないです。)このため、ある程度手直しのいらない品質を求める場合には、60万円~が目安になるでしょう。
高額でも品質の低いライターもいるため、見極めが必要です。
デザイン、印刷製本、流通費
表紙や帯、化粧箱などの装丁デザインを作成する費用、印刷し製本する費用、取次店や書店へ支払う費用の合計です。
デザイン費は数万円~20万円程度です。
印刷製本は一般的なビジネス書200ページの並製本2,000部で、80万~200万円程度です。
流通費は配送にかかる費用、保管にかかる費用、売上に対し(書店等の取り分として)35%~40%程度がかかります。
デザインは装丁デザイナーもピンキリで価格差があります。
印刷製本は品質差はないですが、価格差は大きいです。ブランド力のある出版社ほど高額になる傾向です。
流通費の中心である書店等の取り分は各社大差なく、その他の倉庫代等で差分が生まれる構造です。
広告宣伝費
広告や書店営業にかかる費用です。媒体に支払う費用のほか、運用手数料が発生する場合もあります。
Web広告は1万円程度の少額から、予算に合わせて出稿できる場合が多いでしょう。運用手数料は各社異なり、無料から25%と幅があります。(少額の場合は固定額のケースも)
新聞広告等は、専門の代理店経由で出稿することが一般的です。安い枠で数万円~全国紙等で25万円~くらいの費用感です。原則、読者の多い媒体、広告掲載面が大きいほど費用が高額になります。
書店営業は、営業件数に対し費用がかかる場合と、注文を獲得した冊数に応じて費用がかかる成果型とがあります。初版2,000部であれば、約30万円の営業用予算を持っておくと良いでしょう。
ブックマーケティングの壁打ち相談を受け付けます
月にお引き受けできる件数は限られてしまいますが、無料でブックマーケティングのご相談を受け付けています。60分~120分程度、オンライン会議形式で気になる点や具体的な施策アイデアのご相談等に対応いたします。
マーケティング部門で、施策案として検討中の場合など、情報収集にも利用いただけます。
ご希望の際は、お問い合わせフォームより「ブックマーケティングの相談がしたい」とご連絡ください。