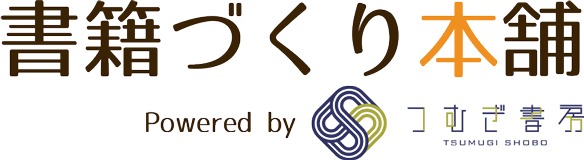自費出版をする上で装丁はとても重要です。本のデザインを決める重要な要素(工程)であり、本の売上を大きく左右します。本記事では自費出版で重要な装丁について基礎知識を解説しましょう。
装丁とは
本の装丁とは表紙や扉、カバー、帯などのデザインや仕様を言います。化粧箱入りの書籍では、箱の作りも含まれます。装丁作成は、主に本の外側をデザインしていく作業であり、本の顔とも言える部分をデザインします。装丁作業が本の売上を左右するといっても過言ではありません。
装丁は既成デザインとオリジナルデザインがある
装丁には既製デザインとオリジナルデザインの2種類があります。たとえば、新書のように既存のフォーマットをベースにすることが既製デザインです。ゼロからデザインを作る場合はオリジナルデザインと呼ばれます。小説の世界観を表紙に組み入れたい場合や、ご自身で撮影された写真を使用したい場合では、オリジナルデザインの装丁を選択すると良いでしょう。
装丁が担う役割
装丁は本の顔であり、文字を読まなくても内容をイメージさせるのが大きな役割です。たとえば、装丁によって本のジャンルが想像させられます。実際に手に取ってくれる人を増やすために装丁は重要です。また、書棚に飾った際の美しさを重視し、装丁をデザインするケースもあります。
原則は、ターゲット読者の目を引き、実際に手に取ってもらうことが装丁の重要な役割です。(非常に本質的な面では、書籍の本文ページを保護し、長期保管に適した状態にする役割も含まれます。)
自費出版ならオリジナルの装丁も作れる
自費出版であればオリジナルの装丁を作れます。オリジナルの装丁を作るまでの流れを紹介しましょう。
ヒアリング
まずはヒアリングが行われ、どのような装丁にするのか打ち合わせをします。具体的な要望やイメージを伝えることで、デザインプランを立ててもらえるでしょう。絵や題字などを自前で用意することも可能です。
表紙や帯の用紙へのこだわりがある場合、早い段階で相談しましょう。用紙の選択が変わることでデザインが変わることもあるためです。(用紙により、細かな線がにじむ特性や、ベタ塗りがきれいに発色しないなど考慮すべき点があるためです。)
デザイン案の提案
ヒアリングをした内容に基づいて、デザイナーがデザイン案を作成します。プロのデザイナーは意図してヒアリング内容から少し外した案も作成する場合があります。
デザイン案をもとにヒアリング
提示されたデザイン案をもとにして再びヒアリング(打ち合わせ)をします。何か問題や要望があれば、伝えることで反映されます。
ヒアリングをもとに修正
ヒアリングした内容にもとづいてデザイン案の修正が行われます。修正の回数に制限が設けられていることがあるため注意しましょう。デザインのニュアンスはなかなか言葉で説明しにくい場合が多いでしょう。書店などでイメージに合致する書籍を探し、書名を伝える方法も一つのアイデアです。
デザイン完成・装丁の印刷
デザインが完成すると、印刷を開始します。色味が希望とズレていないか確認する「色校正」をしたい場合には、契約段階または印刷開始前に相談しましょう。
(多くの自費出版で、色校正は追加費用のかかる追加サービス扱いです。)
デザインを持ち込むことも可能?
装丁のデザインを持ち込むことは可能です。また、ご自身で絵や写真だけを持ち込み、相談をしてデザイン案を提案してもらうこともできます。
デザインを持ち込む際には、用紙のサイズ、塗り足し、JANコードが入る箇所とサイズなど重要な事項がありますから、事前に確認すると良いでしょう。
表紙以外をこだわることも
装丁の中心は表紙ですが、それ以外にもデザインでこだわるべき部分は多くあります。具体的にどのような要素にこだわるべきなのか説明しましょう。
扉
扉とは本文の冒頭、あるいは章の始まりに差し込まれるページのことです。扉に文字や絵を印刷できます。扉を色のついた用紙にすることでインデックスとして活用することも可能です。
片袖折り
片袖折りとはZ折りとも呼ばれます。本の2倍の大きさの紙を折り込む加工のことです。たとえば、年表や地図などを途切れなくページに印刷したい場合には片袖折りが適しています。
見返し
見返しとは表紙と本文の間にあるページのことです。表紙の裏面に貼り合わせる色紙、本文側にある色紙が見返しと呼ばれます。単に飾りとして機能するだけではなく、冊子を補強して耐久性を高める効果があります。見返しを工夫することで本文への導入効果を持たせることもできます。
遊び紙
本文の前にある何も印刷されていないページのことを遊び紙といいます。たとえば、遊び紙に色上質紙を挿入して雰囲気を高めることが可能です。あるいは、タントやファーストヴィンテージといった紙を使うケースもあります。
PP加工(ポリプロピレン加工)
薄いフィルムを表紙に張ることをPP加工といいます。耐久性を向上させるだけではなく、高級感を持たせられるのが特徴です。光沢があり、イラストや写真につやを与える効果もあります。書店に並ぶ多くの書籍は、カバーにPP加工が施されているケースは多いです。
光沢があるものをグロスPP加工、つやを消したものをマットPP加工と呼ぶ場合もあります。
クラフトケース(ブックケース・化粧箱)
クラフトケースとは書籍を収納できる箱のことです。複数冊をまとめて出版する場合はクラフトケースを用意しておくとまとめて収納できます。保存性に優れ、高級感が出ることから長期保存を前提とした高額な書籍で採用される場合があります。
布クロス表紙
本の表紙の材質を布クロスにできます。高級感を演出できるのが特徴です。
穴あけ加工
穴あけ加工とはパンチ穴によって穴を開ける加工のことです。バインダーにファイリングできる冊子を作れます。
装丁デザイン費用の相場は?
装丁デザインの費用は装丁の内容により異なります。一般的な費用相場としては装丁デザイン一式を依頼する場合で10万円程度かかるでしょう。著名な装丁家に依頼する場合は、この数倍かかることもあります。カバーや表紙、帯、本扉などまとめてデザインを任せられます。
まとめ
自費出版では装丁にこだわることで、仕上がりは優れたものとなり、本の売上アップを期待できます。多くの出版社でオリジナルの装丁を作ることも可能です。自費出版を検討する際には、装丁にもこだわりましょう。