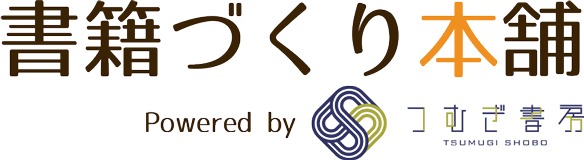企業出版とは?
企業出版とは、法人や個人事業主が、自社の集客力強化・ブランディング等を目的に企画し、印刷製本・流通させる出版形式を指します。
原稿執筆者は多くのケースで経営者、広報部やマーケティング部の担当者です。
別名:カスタム出版、ブランディング出版
企業出版の目的
- アウターブランディング:顧客や取引先などを対象にしたブランド強化。
- インナーブランディング:社員、採用予定者などを対象にしたブランド強化。
- 集客:書籍型の直接集客、他媒体経由の集客効率の改善、権威性の獲得。
企業の理念や製品に関する物語などを書籍化し、ブランド好感度を高めることや社員の愛社精神を育む狙いはよくある一つです。
その他、書籍からメルマガ登録を促すケース、書籍著者という権威性をもってセミナーなどの集客効果を高めたり、講演依頼や寄稿等の引き合いを増やし、間接的に効果を狙うケースもあります。
企業出版の費用
企業出版の費用は、依頼企業が全額負担します。
仕様や部数、宣伝や営業の程度により費用は幅広く、標準的な価格帯を以下に示します。
- 最小限で出版物を世に出す:30~40万円
- 数千部印刷し、書店に並べる:150~400万円
- さらに書店営業や交通広告・新聞広告をうつ:200~800万円
より詳細な費用に関する点は、次の記事「企業出版の費用」にまとめました。
企業出版のメリット・デメリット
メリットは目的について書いた点とも繋がります。
ブランディング効果や権威性を獲得できる点、マーケティングや営業の数字改善に繋がる点、採用活動や現社員のエンゲージメント改善はメリット(狙い)とされているケースが多いです。
メリット
- 書籍を販売し儲けることが目的ではないため、出版社の都合にあわせず、書きたい内容でまとめることができる。
- 書籍の販売にのみ使用できる販路やチャネルを利用できる(書店店頭、新聞書籍広告欄、Amazon広告など)。
- 長期的な情報資産になる、継続的な効果が期待できる。
デメリット
- 費用負担がある。
- 作業工数がかかる。
- 細かくPDCAを回すことができない。
出版という形態であるため、WebサイトやLPのようにリリースした上で改善を加えていくことは現実的ではありません。
このため、制作のチェック一つをとっても作業工数がかかります。
他媒体での広告と比較した場合、マスと比較すれば安価ですが、Web広告との比較では、まとまった支出が必要になる点はデメリットです。
ここまでで挙げてこなかった点として、パブリシティ獲得との相性が良い点に少しだけ触れておきます。メディアが専門家のコメントを必要とした際、書籍を調べ、該当著者に出版社経由でアポをとるケースがあります。研修やセミナー講師の選定時に書籍を読んだ上で、相談に至るケースも見てきました。
自社のオウンドメディアなどで発信することと比較した場合、パブリシティ獲得においては優位な点があろうかと思います。
メリット・デメリットは別ページで詳細にまとめました。詳しくは企業出版のメリット、デメリットページを参照してください。
自費出版や商業出版との違い
企業出版と自費出版、商業出版の違いを表にまとめます。
| 比較項目 | 企業出版 | 自費出版 | 商業出版 |
| 主な目的 | ブランディング、マーケティング、採用強化など企業の経営課題解決 | 個人の表現、自分史、研究発表など「本を出すこと」が目的 | 書籍の販売による利益 |
| 費用負担者 | 企業(著者側) | 個人(著者側) | 出版社 |
| 企画の主導権 | 企業(著者側) 企業の目的達成のために、企業主導で企画を立てる | 個人(著者側) 著者が書きたい内容を自由に決められる | 出版社 「売れる本」にするため、読者ニーズを最優先に企画される |
| 出版のハードル | 低い 費用を負担すれば、原則出版可能 | 低い 費用を負担すれば、原則出版可能 | 非常に高い 出版社が「売れる」と判断した企画のみが出版される |
| 印税・収益 | 発生する場合もあるが、目的は印税収入ではない。 書籍を活用した事業利益の獲得を狙う。 | 発生する場合もあるが、出版費用を回収できるケースは稀。 | 著者に印税(通常5~10%)が支払われる。 |
| 流通・販促 | 程度を選択できる。 企業の目的に合わせ、書店流通させない場合もある。 | 程度を選択できる。 流通させない、または小規模なことが多い。 | 出版社が全国の書店への配本や販促活動を主導する。 |
| メリット | ・企業の信頼性、権威性が向上 ・競合との差別化 ・質の高い見込み客や人材を獲得 | ・自分の好きな内容で本が作れる ・記念品や自分史として形に残せる | ・費用負担なしで出版できる ・印税収入が得られる ・全国規模での知名度向上が期待できる |
| デメリット | ・数十万~数百万の費用がかかる ・制作に時間と労力がかかる | ・費用がかかる ・部数や販促が限定的であれば、読者数も限定される | ・出版のハードルが極めて高い ・内容は出版社の意向が強く反映され、自由に書けない |
企業出版と自費出版の違いについては、こちらのページで詳細を解説しています。
企業出版の依頼から販売までの流れ
相談、企画
この段階が最も重要で、「なぜ出版するのか」という目的を明確にします。
出版社への相談・見積もり
企業出版を手がける複数の出版社に連絡を取り、出版の目的や要望を伝え、費用やサービス内容について見積もりを取ります。
企画立案・契約
出版社を決定し契約後、編集者と具体的な企画の打ち合わせに入ります。打ち合わせで大切にすべき点は次の2つです。
- 出版目的の明確化: 「企業が抱える課題解決」「ブランディング」「集客」「採用強化」など、出版で何を達成したいかを決定します。
- ターゲット読者、テーマの決定: どのような読者に向け、どんな内容にするかを決定します。
制作
決定した企画に基づいて、書籍の形にする作業です。
原稿作成
著者自身が執筆する場合や、出版社が手配したプロのライターが取材・執筆を代行する場合があります。最近では原稿を大方執筆し終えた段階で出版社にご相談されるケースも増えています。
編集・校正
原稿の文章表現を整えたり、情報の正確性を確認したりする編集作業を行います。誤字脱字、事実誤認などをチェックする校正作業を複数回行います。
レイアウト・DTP・装丁(カバーデザイン)の決定
本文のデザインやレイアウトを決定し、印刷用のデータ(DTPデータ)を作成します。書籍のタイトル、キャッチコピー、表紙のデザインを制作・決定します。書店で手に取ってもらうための重要な要素です。
プロモーション・販売
書籍を印刷し、読者の手元に届けるための工程です。
印刷・製本
最終チェック(校了)を終えた印刷データを印刷会社へ入稿し、印刷・製本を行います。この工程には2週間~4週間ほどかかります。(繁忙期は2月~3月です。)
出版・流通
完成した書籍が、出版取次(問屋)を経由して、全国の書店やオンラインストア(Amazonなど)に流通・配本されます。企業出版でも商業出版と同様に、書店での販売が可能です。
プロモーション活動
目的達成のためにプロモーションを行います。(目的によっては一切販促しないケースもあります。)
Web広告、新聞広告、書店での展開、出版記念イベントなどを組み合わせ、ターゲット層に書籍の存在を周知し、企業のメッセージを届けます。
成果の分析
書籍の販売状況や、それによって得られた企業の問い合わせ増加、ブランディング効果などを分析し、今後の戦略に活かします。
一般書店での販売数はある程度精緻な数字が見えるまで約6ヶ月間が必要です。
企業出版の書籍売上金はどうなるか
書籍が書店で売れ、その売上から書店や取次がマージンを受け取り、残ったお金は出版社に入ります。
この出版社に入った売上金の一部(またはほぼ全額)は、著者(ここでいう依頼主の企業)に入ります。
具体的な割合や計算方法など、細かな点は、企業出版の印税(売上分配金)でまとめました。
企業出版を成功させるコツ
企業出版を成功させるコツとして、最も重要なことは「何を目的にその書籍を作るか」を明確にすることです。
「自社がターゲットとする年齢層への認知度がイマイチなので、その層の認知度アップを図りたい。」
「自社サービスを使っているユーザーは増えてきている。しかし、似たようなサービスを打ち出している競合も出てきている現状だ。ゆえに会社としての信頼性を高め、他のサービスにユーザーが流れていかないようにしたい。」
「新しい自社商品をリリースする。その商品の訴求のための営業ツールとして、何か活路を見出したい。」
など各企業での課題や解決したいことは異なると思います。ですので、何を目的に企業出版していくかを明確にする作業を、一番初めにすることが大事です。
そこから、担当の編集者に書籍の目的を伝え、その目的を達成するためにはどのような書籍の内容・構成・デザインが適切かを共に考えていくと良いでしょう。編集者はその道のプロでもあるので、明確な目的が定まっていれば、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。その他に大事な要素としては、「届けたい層にリーチできる仕組みを構築すること」が挙げられます。
目的を達成できる内容・構成・デザインの書籍を制作できたとしても、企業側がターゲットとする人たちに認知され、見てもらえるようにしなければ意味はないでしょう。従って、適切な販路の選択、ターゲット層へ認知させるための広報活動は必須事項と言えます。
→当サイト「書籍づくり本舗」の企業出版サービスの詳細はこちら