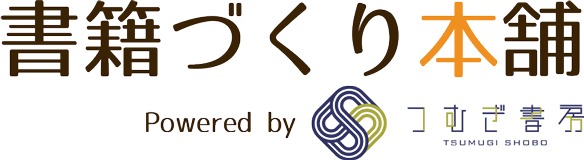本ページでは、企業出版と自費出版の違い、同じ点をまとめます。
端的な結論としては、企業出版は自費出版の一種であり、自費出版の中でも企業活動の一環で取り組む出版を指します。伴って大枠は同一です。
企業出版と自費出版の項目比較表
差異を確認しやすいよう、表にまとめています。
| 項目 | 企業出版 | 自費出版 |
| 出版の目的 | 企業の課題解決(ブランディング、集客、採用強化、販促など、事業成果への貢献) | 個人の作品・研究成果の発表、記念、自己実現、伝承など(書籍を制作すること自体が目的) |
| 著者または依頼者 | 法人・法人代表・個人事業主 | 個人(作家、専門家、一般の個人など) |
| 費用負担者 | 法人・個人事業主(依頼者)が全額負担 | 著者(個人)が全額負担 |
| 読者ターゲット | 企業の潜在顧客、既存顧客、株主、採用候補者など、特定の目的を持つ読者層 | 一般読者、親族、知人・関係者、または特定分野に興味を持つ読者層 |
| 企画、制作の主体者 | 企業(企業の課題解決を目的としたマーケット・インの視点が重要) | 著者(著者の意図が中心) |
| 著者の名義 | 企業名、または企業の代表者名 | 個人の実名、またはペンネーム |
| 在庫の所有者 | 企業(依頼者) | 著者(個人) |
| 流通、販売 | 出版社の流通ルート(全国書店、Amazonなど)を通じて一般に販売されることが多い(販売戦略が目的達成のために組まれる) | 出版社の流通ルートに乗せることも可能だが、著者自身が知人やイベントで直接販売するケースも多い |
企業出版を取り扱う国内全ての出版社において、上掲記述に合致するとは限りません。イレギュラーな点を含めて、以下で補足します。
出版の目的
通常、企業出版は直接的、間接的に売上増やコスト減を狙ったものです。
一部例外として、周年記念誌や社長退任に伴う自伝など、事業活動への影響を期待しない出版が含まれます。
著者または依頼者、費用負担者
企業のブランディングを目的にした出版ですが、社長個人が個人の支出として自費出版するケースがあります。費用負担が個人ですが、実態としては企業出版と扱われるものです。
読者ターゲット
企業出版では、例外的に読者ターゲットを定めないケースがあります。
具体的には、経営者の個人プロフィールに著書を記載することで権威性を高めることが狙いで、販売することを目的にしていないケースです。伴って、売る視点を持たず、専門分野に尖らせた内容重視で作成されます。
企画、制作の主体者
企業出版、自費出版のいずれでも、制作の進行役や作業の補佐に出版社スタッフが介在します。サポートの程度は、依頼者の要望に応じて決定されます。
著者の名義
企業出版では、稀に部署名やプロジェクト名などを著者名とするケースがあります。
企業名よりも製品名の認知を高めたいケースなどで、製品名を関した部署名を著者とすることもあります。
在庫の所有者
在庫の管理は出版社や倉庫業者が担うことが通常です。
完成した書籍の所有者(物の権利を持つ者)は通常依頼者ですが、一部出版社で完成書籍は出版社の所有になるケースがあるようです。
流通、販売
記念誌などで流通させないケース、無償配布が中心のケースがあります。
企業出版と自費出版で原則同一の項目
売上金(印税)
書籍の売上から、書店や取次店、その他流通経費を除いた残金は、依頼者に支払われます。これは企業出版・自費出版で同一です。
出版社が書籍売上から利益を取るケースがあり、利益の割合(数%~40%)は各社様々です。
定価
いずれの場合も、書籍の定価は依頼者が決定できます。
極端に高額な設定とした場合、国会図書館への納本時に代償金(定価の5割ほど)が支払われない可能性があります。
また極端に高額、低額の場合、流通に乗らない可能性があります。高額な書籍は弁償リスクも高くなることに起因し、低額の場合は書店や取次店が売上マージンを取れないことから引き受けないことへ繋がります。
著作権
いずれの出版形態でも、著作権は執筆者に属します。
自費出版では著者個人が著作権を持ち、企業出版では、業務時間内に従業員に執筆させるケースでは、企業が著作権を持つことが一般的です。
類似著作物への使用
いずれの出版形態でも、他媒体や加工利用を制限されることはありません。(一部制限を課す出版社もあり)
ただし、同一の原稿で書籍を作ることには制限を加えるケースがあります。これは読者の視点に立った際、混乱が起き得るため制限していることが多いでしょう。
つまり、セミナー資料に転載できるか、ブログでの公開ができるかなど、書籍ではない用途で制限がないか確認すると良いでしょう。
出版権
通常は、出版社に出版権を設定します。稀に複製権のみを与えることで、出版するケースがあるようです。第三者による著作権侵害が発生した場合など、出版社が関与しづらく、著者(依頼者)負担も重いことから、複製権のみとするよりも、出版権に期間を定めるケースが現実的かと思います。
増刷
いずれの場合も、依頼者(企業や著者)が増刷の意思決定、費用負担をします。完成書籍の所有権が出版社に設定されるケースや、売上金から出版社が受け取る割合が高いケースで、増刷費用を出版社が負担するケースがあるようです。
(売上金で増刷にかかる費用を補えているため)
増刷の意思決定が出版社になる点、増刷を考慮した定価設定となる点(依頼者は、定価の最終決定ができない)を事前に確認し、考慮した上で判断できると良いでしょう。