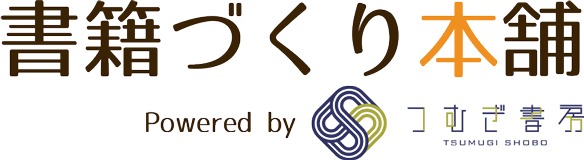企業出版にかかる費用を詳細に説明します。
相場感を理解いただくこと、個別具体的な費用もいくつか紹介し、自社と近しい刊行物のケースからおおよその費用を把握いただくことを狙いにしています。
企業出版の相場、価格幅
企業により叶えたいことが多様であるため、ひとまとめにした相場というものがありません。
具体例を挙げて、相場を見ていきます。
最小限、最小価格
何をしたいかではなく、とにかく最小価格で書籍を完成させることを目指す場合です。
ご自身でWordを用いて本文データを作成し、無料ソフトで表紙画像を作成します。印刷と販売はAmazonPODを用いるとした場合、費用は無料です。
書店で見る書籍と比較すれば、レイアウトやデザインなど品質面で採用されるケースはないであろう方法ですが、AmazonPODというAmazonが提供するパブリックオンデマンド(注文ごとに印刷製本する制作手法)で初期費用はかけずに実現可能です。数冊書籍がほしいとなれば、都度Amazonに注文することで完成書籍を手に入れます。
150ページ、並製本、100部印刷、販売しない
標準的な価格帯は、25万円~200万円です。
社内で原稿を準備し、本レイアウトや表紙のデザイン作成は専門家に任せ、並製本での印刷製本までを出版社や印刷会社に委託する場合です。
(並製本=書店で多く見かけるソフトカバーがかかった書籍。新書や実用書などの多くはこの製本方法)
書店での販売はせず、販促等で手で配ることを想定しています。
価格帯が幅広いですが、相場は40~50万円ほどです。100万円を超える価格帯は、大手出版社の場合です。
200ページ、並製本、1000部印刷、書店販売
企業出版を検討する方々に最も多いケースがこちらかと思います。
標準的な価格帯は、70万円~400万円です。
社内で原稿を執筆し、出版社の簡易な編集や校正サポートを受け、本文ページ・表紙・カバーのデザインから印刷製本、取次店を通して書店へ配本するところまでを出版社が担います。
一般書店に500部程度配本する想定です。
(配本する=出版社が書店に対し書籍を預け、書店は販売するしない含めて自由に判断し、一定期間経過後に余った在庫を返品できる仕組み。)
2025年時点、希望する部数の配本が難しくなりつつあります。書店営業を実施し、配本数を積み上げる施策とセットで検討すべき点が含まれます。
(書店営業のお話は後述)
相場は100万円前後です。定価が高額な商品の場合や返本率が高くなると想定される場合、流通にかかるコストが数万円~10万円ほど追加される場合があります。300万円前後の価格になるケースは大手出版社のみです。
200ページ、並製本、2000部印刷、書店販売、書店営業+売上ランキングランクイン、新聞広告、Amazon広告
しっかり予算組んで取り組まれる企業はこのあたりも多いです。
標準的な価格帯は、300万円~1000万円です。
書籍の作る工程は前項と同一で、異なる点は次です。
- 書店へ訪問、FAX、電話で営業し、該当書籍を注文(仕入れ)していただく
- 選定した書店でランクインできるよう、在庫の買上げを実施する
- 全国紙の書籍広告欄に出稿する
- Amazon内の検索時、買い回りで広告を出稿する
2000部のうち、1000部超を書店へ配本しようと考えた場合、営業なしでは実現が困難です。
このため、出版から書店へ該当書籍をご紹介し、仕入れていただけるようご案内します。仕入れてくださった書店には、POP等の販促資材を郵送することもあります。
(POPははがきサイズの印刷で数もさほど多くないため、費用差分はほぼありません。)
批判的な意見もある方法のため、細かな話は割愛しますが、書店で掲示される週間売上ランキングは、その店舗での売れた部数を計算している場合が大半です。このため極端な言い方をすれば、1位になるであろう部数を注文し購入すれば、一人で大量購入したとしてもランクインします。大量に購入し書籍を担いで帰るのは大変ですから、ご興味あれば弊社までお問い合わせください。
その他の費用に影響のあるオプション
ページ数の増減、印刷部数の増減は分かりやすく費用に影響します。
その他にもいくつか作業の追加や仕様変更により費用が変わる点があるため、ここにまとめます。
執筆の代行、編集
いわゆるゴーストライターが企業に変わり、書籍原稿を執筆することがあります。
費用目安は4万文字で40万円、8万文字で80万円程度です。
(ライターの腕や実績で上下します。通常、取材が伴うため、取材回数や移動回数も影響します。)
編集は企画とは異なり、構成や具体的な文章の改善を行う場合を指します。
15万円~40万円程度が中心で、校閲(ファクトチェック)を含めると更に高額になります。特に医療や法律、最新研究の分野など、チェックの難易度が高いものは高額になりやすいです。
素読み校正
校正刷りをそのまま読み、誤字脱字や表記揺れを確認する作業です。
校正は専門業者が多く、出版社も外注しているケースが多いでしょう。
標準的な費用は1冊分で15~20万円程度です。分量や短納期など、事情に応じて追加が発生します。
その他、読み合わせ校正や突き合わせ校正なども必要に応じて外注可能です。
高級な紙材、上製本
本文用紙、表紙用紙、カバー用紙など標準的な紙剤を用いず、高級用紙を用いる場合には原材料差額がある分、費用は上昇します。
その他、箔押しなどの特殊加工、正方形などの特殊形も費用が上がる場合が多いでしょう。
上製本(ハードカバー)とは、辞書や絵本で多く採用される製本手法で、書籍の裏表・背にボール紙を入れくるみ巻きします。耐久性が高まりますが費用も大きく上がります。
上製本の費用は並製本と完全に別物であるため、(企業出版で採用するケースは販売を目的にしない記念品が中心であるため)ここでは詳細な費用を割愛します。
電子書籍
紙の書籍とセットで電子書籍を作成、リリースする場合、EPUBに代表される電子書籍用フォーマットの作成費がかかる場合が多いです。
リフロー型の場合、文字中心の原稿で数万円~10万円ほど。写真や図版が多くレイアウトが複雑な場合は5万円~15万円ほどが相場です。
(リフロー型とは、スマホやタブレットなど端末の幅にあわせて文字サイズやレイアウトが自動調整される形式です。対義語はフィックス型)
イラスト、図版
表紙で用いるイラストや本文内の挿絵などをオリジナルで作成する場合、グラフや表などを作成する場合に作業費がかかるケースが多いです。特にExcelやPowerPointで作成した図版はそのまま印刷用データにすると粗さが目立つため、Illustratorで図を作り直すことが一般的です。
(そのまま使えないこともないですが、細かなものは作り直すことを想定しておくと良いでしょう。フルカラーの図をモノクロで刷る場合も、分かりやすく作り直すケースが多いです。)
イラスト作成費はピンキリで1点あたり数千円から3万円程度が中心です。著名なイラストレーターに依頼する場合、1点あたり10万円程度の予算を別に確保します。
翻訳権
洋書の翻訳版を出版する場合や、引用と認められる範囲を超えて、洋書などから転載する場合、原書の翻訳権を必要とするケースがあります。
翻訳出版権(版権)の交渉を原書の著者+版元(出版社)とし、契約を取り交わします。通常は日本の出版社と版権エージェントが代行します。
ベストセラーは除き、一般的なビジネス書で交渉代行費が10万円ほど、原書の著作権利用料が売上の6~9%程度になるでしょう。この著作権利用料は最低額が定められる場合が多く、20万円台~40万円台程度です。
(引用と認められる範囲については、「引用の主従関係」について調べてみると良いでしょう。)
その他、初版の部数や広告宣伝の程度など、取り決めはケース・バイ・ケースであるため、企画の早い段階で版権に空きがあるか含め、確認されることを推奨です。
帯
「◯◯氏推薦!」や「◯◯部突破!」といった購入を後押しするような帯を見かけたことがあろうかと思います。増刷時から帯をかける(付ける)場合もあれば、初版時から帯をかける場合もあります。
ご自身で帯文を書いてくださる著名人をつれてくるケースもあれば、書籍の内容にあった著名人候補を考え、個別に打診していくケースもあります。
帯を書いてくださった方に謝礼を払うことが多く、数万円から数十万円です。売上に応じた金額設定とするケースも稀にありますが、生々しくなるため、ここでは割愛します。
出版社毎の費用差分
各社各々のスタンスがあるため、費用差分への考え方も多様です。
一言に収斂させると「ブランド」の差分が費用の差分である、この考え方がある程度正確な表現だと考えています。
ブランドの効果は、見え方だけでなく、書店への配本がしやすい・読者が出版社名で内容が優れていると判断しやすい・パブ獲得効果が高まりやすい、この3点に繋がります。
中小中堅出版社は標準的な費用帯で、知名度のある出版社(遠慮しつつ記載するとD社、P社、T社、F社)はブランド力相当額が乗った費用帯だと理解すれば良いでしょう。
時々、費用が高額なサービスは、コンサルティング力や企画・戦略策定力で優れているといった話を耳にします。これは中小大手関係なく、担当者の能力次第な話であるため、眉唾ものだと思っています。
(大手の幹部だった方が独立起業し、中小出版社社長になったから能力が落ちるという話もありえない訳です。)
企業出版の費用を見積もる際の事前準備
繰り返し見積もりを取ることは手間になるでしょうから、見積もりを取る前に準備できる点は準備し、二度手間・手戻りを避けて進めると良いでしょう。
企画段階からラフに相談する場合は、ここで挙げる準備をせずでも良いと思います。
1.目的の整理
目的があれもこれもになるケースが多いですが、企業出版を上手に活用されている企業ほど目的が明快です。特に「誰」の部分で、外部に対してか内部(従業員)に対してかは進め方に大きな違いがあるため、クリアにできるよう準備します。
※内部への理念浸透などを目的にする場合、広告宣伝費は原則不要であるため、費用面で大きな差がでます。
2.仕様、予算の設定
ここで重要な点は、「並製本・上製本」の選択です。
一部の特殊ケースを除き、並製本を選択することをおすすめします。
※特殊ケースの例として、絵本や写真中心の社史、記念誌、500ページを超えるビジネス書、超ニッチな専門書が挙げられます。企業出版で発行する書籍の多くは、定価1400~2000円あたりで値付けすることが多いです。売らない前提、もしくは医療書に代表される定価4000円程度の設定が当たり前の領域の場合には、上製本を検討すると良いでしょう。
予算の設定は、前述の相場を参考におおよその金額を定めておきます。
予算は出版社に伝える必要はありません。広告宣伝や書店での展開など、幅広い提案を必要とする場合には、予算にゆとりがある旨を出版社に伝えることで、多彩な提案を引き出せると思います。
3.原稿の執筆担当、目標完成時期
中小企業では経営者自ら執筆するケースも多いです。百名超の企業であれば、出版プロジェクトの担当者に任せる場合もあるでしょう。
原稿から外注するか否かで大きく制作工程と制作期間が変わってくるため、考えをまとめておきます。
「経験がなく、書き上げることができるだろうか?」とご相談いただくことは非常に多く、出版社側もこの点は理解しています。ここで大切なことは、執筆にかかる作業工数を確保できるかです。
新書相当(8文字程度)の初稿を書き上げるのに、スムーズに進めて100時間はかかります。発売したい時期がだいぶ先であれば、月に15~20時間程度の作業時間であれば確保できそうだ、1ヶ月以内に原稿を書き上げるスピードで進めたいがその時間は捻出できない、といった具合に目標完成時期とセットで検討すると現実的な計画になるでしょう。
企業出版の費用対効果、費用の回収率
記念誌のように費用対効果を求めない、売るつもりでないケースは本項は読み飛ばしてください。
費用対効果
アウターブランディングの効果を測る場合、メジャーな方法がいくつかあります。具体的にはブランドリフト調査やブランド認知度調査・好意度調査が代表格です。
書籍は、テレビCMなどと比較し読者数が限られるため、メジャーな計測手法では現実的ではありません。このため、販売数か、読者の反響の程度を計測することが良いでしょう。
(反響:SNSやネット書店での口コミ、読者であることが確認できた購入数)
インナーブランディングの場合は、社内アンケートやeNPS(従業員ネットプロモータースコア)を用いることが多いでしょう。働き方改革の影響もあり、年1回の定点計測している企業も増えました。発売前(従業員が書籍を手に取る前)との比較ができるよう、書籍の企画段階から着手することがおすすめです。
費用と効果を比較する都合、リーチが取れたこと、良い反響やスコアが上がったことに対する価値を金額換算し定めておきます。
自社サービスの紹介セミナーを告知、集客する際に1申込み1万円かけていたと仮定すると、書籍1冊売れた価値は5000円、1万円、2万円と仮ぎめできるでしょう。(未来、成約に至った数値から改めて割り戻すなどの作業はあって良いと思います。)
eNPSの平均が1改善することで、離職率が◯%改善するのであれば、採用コストや教育コストの減少効果を算出できるでしょう。
費用の回収率は、書籍の売上を差し引いた持ち出し費用をもとに計算します。
企業出版における売上金の扱いは、各社様々です。どの程度の割合で依頼企業に戻されるか確認しておきましょう。(書店や取次店の取り分があるため、売上の55%程度が計算上の最大値です。)
企業出版の費用を抑えるには
はじめに、あまり現実的ではない方法をご紹介し、続いて通常の出版方法における費用の抑え方をまとめます。
1冊あたりの費用を抑えるには、一度に多く刷るという解決策ですが、ここでは総額を抑える観点で記載しています。
電子書籍、POD(あまり現実的ではない)
Amazon Kindleや楽天Koboなど電子書籍のみを発売する方法です。紙の印刷データ作成と比較し、データ作成費は安価であり、印刷や物流が不要であるため、無料に近しい費用で発売できます。
PODとは、プリント・オン・デマンドの略称で、代表的なサービスはAmazon PODです。印刷用データをAmazonに預け、注文が入るごとに印刷・発送をAmazonが担います。こちらも在庫を持たず、売れた部数のみ印刷するため、費用は売上から差し引く形となり、実質手出しはほぼなく始められます。
いずれも企業出版として利用しているケースは稀です。(個人事業主の方が利用されているケースは見かけます。)
制作の内製
執筆、編集、DTPデザインを自社内で担うことで、印刷費と流通経費だけに支出を絞る方法です。
社内にデザイナーが在籍するケースでは、費用面の理由だけでなく、内製して進めるケースがあります。
仕様の簡素化
オプションの項でもご紹介しましたが、並製本の採用、標準的な紙材の使用、見返しや帯を付けない、ページ数を絞る、本文にカラーは含めないなど費用を抑えられる点を確認します。
書店で売られている本を見てみると分かる通り、多くの書籍は仕様を最低限にしています。
販売方法の絞り込み
書店店頭での販売をせず、ネット書店や自社通販などに絞ることは一つです。
流通経費が削減できるだけでなく、返本の再生費用を含めてコストを下げられます。
(書店へ流通させた書籍は、立ち読みなどでダメージを受けて返ってくることがあります。三面を磨いたり、ソフトカバーを付け替えるなどし、新品の状態へ再生させることが日常的にあり、この費用を削減できます。)
相見積もり
ご説明は不要かと思います。複数社見積もりをとり、費用比較をすることで外注コストを最小限にする取り組みです。
企業出版の費用支払い方法
最後に費用の支払い方法についてです。
企業出版は請求書を発行し、銀行振込で支払うケースが中心です。クレジットカード決済に対応する出版社も多少ですがあるでしょう。
支払いは契約時に支払うケース、契約時に半金・納品時に残金のケース、納品前後で支払うケースと各社様々です。
Webサイトや資料内で支払いタイミングを明示していない場合、個々に与信次第で設定としているケースがあります。