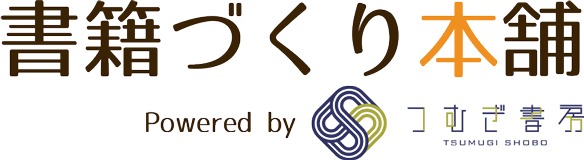本ページでは、企業出版のメリット・デメリットを整理してお伝えし、自社の施策として相性が良いかご判断いただく材料を提供したいと思います。
企業出版のメリット
まず企業出版という手段を用いることのメリットです。
権威性、信頼性を高める
多くの方は著書を持つ方に、その領域における権威性や専門性を感じます。
セミナー講師の自己紹介文に「著書:◯◯(△△出版)」と書かれていることをよく見ると思います。セミナー参加者は、本を出すほどその領域に詳しい講師だと考えることでしょう。
論文の引用に近しい話として、SNSで著書の内容を引用、紹介する投稿を目にします。これも第三者による評価や紹介により権威性や信頼性を高める効果が期待できます。
書店、書籍広告枠という新チャネルを活用できる
書店の棚に陳列される、ポスターやPOPで著者名が掲げられることは、知名度や認知度を高める上で効果があります。当然ですが、書店の本棚には「書籍」しか並べることができません。(手帳や文具、キャラクター商品など開発品も見かけますが、このお話は別途どこかでの機会で)
新聞や雑誌等には、書籍広告用の枠が設けられている場合が多く、こちらも書籍の宣伝目的でのみ、広告出稿が可能です。一般の広告枠よりも安価に出稿できる枠が多いです。
Amazonの書籍用広告枠も同様です。類似書ページを見るユーザーに買いまわりを促す広告は分かりやすい例です。
間接効果が期待できる
著書があることで、講演の依頼を受けたり、寄稿の依頼を受けたりすることがあるでしょう。テレビやラジオ等のメディアが専門家として取材協力を求めてくるケースもあるでしょう。直接的な事業貢献だけでなく、会社や著者の知名度を引き上げることで間接的な貢献に期待できます。
長期間、効果が期待できる
書籍という保存性に優れた媒体であることから、購入者に対し継続的に接触でき、効果が長続きすることが挙げられます。書店での販売期間は永続的ではありませんが、購入者への効果に加え、中古品としての流通経路も加わる場合があります。
伝達情報量が多い
チラシやセミナー等と比較し、書籍には圧倒的な情報量を届けられる点が強みです。多くのビジネス書は150ページ~250ページ程度のボリュームがあり、文字数にすると7万~12万文字相当です。
順序立てて、伝えたい情報を網羅的に提供できる点は分かりやすいメリットと言えるでしょう。
営業や社員教育など、二次利用がしやすい
商業出版と異なり、企業出版で制作された書籍は、二次利用可能な契約が多いです。
書籍の内容を要約したセミナーを作ることもできるでしょう。営業資料やホワイトペーパー内に書籍からの一部抜粋を掲載することもあるでしょう。
インナーブランディングに期待するケースでは、書籍を社員に配布するだけでなく、社内教育資料への展開も容易です。
企業出版のデメリット
次に企業出版を実施する場合のデメリットを整理します。
費用の負担
ブログを書く、チラシを作るといった施策と比較し、高額な費用がかかります。
安価に進めても数十万円、費用の高い出版社で進めると1000万円前後かかってきます。
書籍の宣伝費用は上限がないとも言えますから、広くプロモーションを実施すれば高額になります。
制作に時間がかかる
相当に早いケースでも2か月程度の制作期間を要します。標準的には半年から1年近くの期間がかかります。
印刷製本にかかる期間、取次店の処理・書籍の入出庫・運搬など期間を短縮できない工程がある点には注意が必要です。
競合にも読まれる可能性がある
書店で流通する都合、競合企業に買わせないという制限を設けることができません。掲載する内容がノウハウ中心であれば、競合他社にも書籍の内容が伝わる点は懸念でしょう。
情報更新がしづらい
印刷物である都合、改訂には時間と費用がかかります。
ITの世界で言うアジャイルとは反対にある点がデメリットです。制作に時間がかかる点とも合わさって、情報更新頻度の高いテーマや技術発展速度が早い領域などでは、このデメリットを正しく捉えることが大切です。
情報が届く先の数が限定的
書籍を手にした方が1,000人であれば、情報の伝達先は1,000人です。知人に貸す、図書館が蔵書するなどで範囲は広がりますが、数万人になることは稀でしょう。
テレビCMやYahoo!のブランドパネルなど数百万人、数千万人に届けるような媒体と比較すれば圧倒的にリーチが限定的な施策です。
ただ、購入されずとも書店で目に入る効果や権威性の獲得など情報伝達以外の効果をどう捉えるか、書籍という情報量が多い点とのトレードである点を含めて考えると良いでしょう。