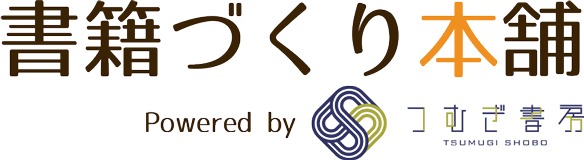企業出版における印税率、計算方法、支払い方法、各社差分についてをご紹介します。
企業出版の印税相場
企業出版における印税の相場は、売上の40%~50%程度です。
正確には、企業出版における売上のうち、書籍を制作した企業に対し、売上の40%~50%程度を分配します。
印税相場を語る上で、次の点を把握すると正しく理解できるため、やや範囲が広くなりますが確認します。
- 印税ではなく、売上分配
- 書籍売上から差し引くコスト
- 出版社はどこで利益を取るか
印税ではなく、売上分配
印税(=著作権使用料)とは、著作物を作成し流布する際に、著作権者に対し支払うロイヤリティです。
企業出版においては、著作権者が企業または代表者であることが大半です。書籍を作成する者が著作権者であるため、著作権者がご自身に対し使用料を支払うという流れが誤りとなるため、企業出版における書籍売上のうち、企業(ここでいう企業出版の依頼者)に対し払い出されるお金は「売上分配金」や「売上金」と呼ぶことが多いでしょう。
書籍売上から差し引くコスト
次に、書籍の売上からどのような種類のコストがどの程度差し引かれるのかを確認します。
あくまで出版社や取次店・書店の個々の契約条件による部分であるため、国内一律同率で運用されているものではない点、ご認識ください。
書店、ネット書店
販売額の20%前半~20%後半が書店の売上になる(取り分になる)割合です。
取次店
販売額の8%程度が取次店の売上になる割合です。
配送、倉庫保管
取次店に支払う「歩戻し金」が定価の数%発生します。加えて、返品があった際の「返品運賃」が別途かかります。これらは取次店の倉庫に対する入出庫に伴うコストです。(返品運賃は返品率の影響を受けるため、状況に応じて増減します。)
通常、書籍の在庫は出版社が管理する倉庫にあります。この倉庫から取次店倉庫へ搬入し、納入します。この納入時の配送コストがかかります。宅配便での納入はできず、指定の方法・伝票での処理が伴います。
返品時は商品が逆走するため、取次店倉庫で受け取り、出版社倉庫に戻す配送が発生します。
どの程度の金額か示しにくいですが、個人宅への宅配便よりも少し高い程度のコストだと認識いただければおおよそ良いかと思います。
これ以外に書店への直送が発生する場合があり、これは宅配便(ヤマト運輸や佐川急便など)を用いるため、通常の法人契約運賃と同程度です。
出版社
次の項の利益に関する内容で詳細を記載しますが、おおよそ数%程度を受け取ります。
出版社はどこで利益を取るか
企業出版における出版社の利益は、通常は書籍が完成し発売した瞬間には確定しています。
大きな括りで言えばBPOですから、納品が済んだ時点で利益がでる想定で値付けをしています。
では流通、つまり書籍の売上から利益は取らないかというと、そういう訳ではありません。
理由は大きく2つあります。
売上増加に伴い、事務処理も増える
よく動く書籍は、書店からFAXが頻繁に届きます。
内容を確認し、取次店へ連携する、倉庫から取次店倉庫へ納入するといった書類仕事や配送業務が増えます。このため、企業出版の値付けの際に、とても売れて事務作業が大量に発生する見立てで設定するか、売れた場合に売上の一部から取らせてもらうかの設計とします。
読めないコストがある
返品コストが代表的で、書店へ配本した書籍の5割が戻ってくるのか、9割が戻ってくるのか、蓋を開けるまで読めないコストがあります。
そのため、売れるほど赤字になっては困るため、ある程度のバッファ(相殺できる程度の利益)を設けておくことが多いです。
企業出版の売上分配金(印税)の計算方法
各出版、分配割合を定めている(または個別の契約で定めている)かと思います。
かかった費用を個別に計算することが現実的ではないため、(複数のタイトルが同時混載で配送されるケースなども多いため)売上に対するパーセントで定めます。
次の条件だった場合と仮定し、計算をしてみましょう。
- 書籍の定価:税込2,000円
- 売れた部数:1,000部
- 分配率:50%
2,000円×1,000部×50%=1,000,000円
売上分配金(印税)の支払方法
ここでのポイントは時期、決済手段、税です。
各社違いはあれど、半年や1か年といった一定期間毎に売上を計算し、先の計算式で分配する金額を算出します。
支払いは、銀行振込による支払いです。その他の支払方法も存在するかもしれませんが、聞いたことがないです。ここでの振込先は、企業出版の契約者の銀行口座です。
最後に税についてですが、売上金であるため、消費税が含まれ、源泉徴収は行われません。
(先の計算式が税込みで計算しているため、ここでも消費税が含まれるとの表現にしています。)
印税は10.21%の源泉徴収を行うことが通常ですが、預かった書籍の売上金であるため、源泉徴収は行わないことが一般的かと思います。
※弊社ならびに当記事編集担当は税の専門家ではありません。詳しくはご契約の税理士等にご相談ください。
やや蛇足ですが、印税ではなく売上になるため、企業出版にかかった費用を仕入れとするか、広告宣伝費とするか考え方が分かれます。(より細部の話をすれば、商品在庫として資産にするか)
企業出版の目的では売上ではないケースが大半で、在庫を売り切っても赤字を想定したプロモーションのケースも多いため、広告宣伝費扱いとされることが多いと聞きます。
こちらも税の専門家にご相談の上、ご判断いただくと良いと思います。
なぜ企業出版の印税率(売上分配率)は各社バラバラなのか
各々自由に設定しており、業界的なルールもないためバラバラになっていることが結論ではありますが、その前提に立ち、「なぜ数%~50%ほどと幅があるのか」を考えてみます。
企業出版を行う企業の多くは、売上を気にしていない
広告宣伝の一環で行うことが多いため、売上が出ないほうが都合が良いと仰る企業様もあるほどで、出版社が売上分配金相当額を留保し、新聞広告等に使うケースもあります。
売れた部数に関心はあるが、数十万の売上金には関心がないケースが非常に多く、そのため一部出版社は分配率を低く設定しているものと考えています。
売上分配を少なくすることで、初期費用を安価な設定にしやすい
当ページの途中でもご紹介した通り、書籍の流通には未確定のコストがあるため、分配率を下げ、売れた場合に十分な利益が確保できる状態にすると、初期費用(出版費用)を抑えやすいです。
そのため、新規依頼を取りやすくなる効果を考え、分配率を下げている出版社はあるでしょう。
当サービスは通常、50%の分配割合です
詳しくは、資料をご確認ください。
⇒企業出版サービスの無料資料