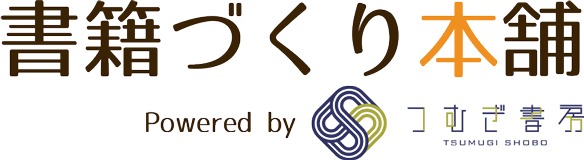自分の作品を世に発表するため、自費出版を検討する方も多いでしょう。残念ながら、自費出版を進める中でトラブルに遭遇してしまうケースがあります。
本記事では自費出版のトラブルの事例とトラブルを回避する方法について解説します。
自費出版とは
自費出版とは自分で費用を負担して書籍を出版することです。
著者自身が書籍を作る中で、初めてのことも多くトラブルが起きる場合もあれば、多くの方は出版社に依頼し出版作業のサポートを受けます。そのため、出版社との間でトラブルが発生する場合があります。
自費出版の主なトラブル
自費出版で起きやすいトラブルの事例を紹介します。
印刷工程のトラブル
出版社などを利用せず、著者自身が印刷用データを作成し、印刷会社に入稿するケースで起きるトラブルです。
印刷データに不備があり、期待通りの仕上がりにならないケースが稀にあります。トンボの位置がズレていた、余白の取り方にミスがあった、色の発色が想像と異なったなどの問題は多いでしょう。
契約内容に関するトラブル
自費出版サービスを提供する出版社との契約内容に関してトラブルになることは多いです。
特に契約期間が終了した後の取り決めや、増刷時の認識違いによる問題は、避けようがある問題のため、気をつけたい点です。
編集・校正ミスによるトラブル
ミスが残ったまま印刷されたというケースは多くあります。出版社等に任せる場合も任せない場合も、大半の場合で最終校正は著者責任になっています。どこまで丁寧に作業しても一定の割合で誤字などは残るものですが、ご自身が満足いく仕上がりになるよう最終校正を丁寧に行いましょう。
費用に関するトラブル
思っていたよりも費用が高くなりトラブルになることがあります。事前に見積もりを受けたときよりも高額になるケースです。
紙材を変えた、印刷部数を増やしたといった分かりやすく費用が変わるケースはトラブルになりづらいです。
一方、本文レイアウトを調整した結果、完成ページ数が想定よりも増えた場合や、デザイン等の修正回数が規定回数を超えたため追加費用がかかった場合等で、出版社と著者間で意見の食い違いが発生するようです。
悪質な業者は論外ですが、ページ数が増えれば費用が増えることは一般的です。著者の希望が制作過程で変わり、作業のやり直しが発生する場合にも追加費用が発生することが一般的です。
どこまでが見積り額の範囲内か、把握しておくことが大切です。
販売についてのトラブル
印刷製本した書籍を、いざ書店へ配本しようとなった際に、希望する部数の配本が叶わないケースです。
タイトルや表紙デザインが配本数を減らしている原因の場合もあれば、営業不足による場合もあります。
10年、20年前と比較し書店数は大きく減少しています。また業界あげての返本率改善への取り組みもあり、希望する配本数に満たないケースは今後も増えるでしょう。
数百部の配本希望では、大きな差は生まれにくいですが、数千部の配本を希望する場合には、契約前に配本についてじっくり相談しておくことが大切です。
(多くの場合、どの程度の営業や広告を実施すると、希望の配本数に近づけるか等のアドバイスをしてくれるはずです。)
加えて、配本と陳列の違いについても把握しておきましょう。出版社と取次店の間で決定されるのは配本数です。多くの出版社は配本数について著者と相談しています。
書店に配本された本が、店頭には陳列されず倉庫で眠るケースもあります。棚の買い上げをしている出版社を除き、書店員が在庫をどのように陳列するかは出版社ではコントロールができない点です。この点を把握した上で販売計画を立てましょう。
詐欺によるトラブル
自費出版で詐欺の被害にあってしまったケースがあります。たとえば、事前に費用を支払った後に持ち逃げされたケースです。本そのものが出版されない場合もあり、裁判沙汰にまで発展することがあります。
なかなか外から財務の健全性を確認することは難しいですから、コンスタントに新刊が出ているかや支払いを複数回に分けることができるかを確認すると良いでしょう。
トラブルを回避するためには
自費出版のトラブルを回避するための方法を紹介します。
契約書をよく確認する
自費出版に関して業者と契約する際には、契約書の内容をきちんと確認しておきましょう。内容について分からない点や疑問点がある場合は、きちんと質問して説明を求めます。不明瞭な点を放置しておくとトラブルの原因になるため注意しましょう。
とくに確認すべき点を挙げるならば、下記でしょうか。
- 書籍の所有権は依頼者にあるか(通常は著者)
- 定価を著者が決められるか(通常は常識的な範囲で自由に決められる)
- 売上の分配割合は(多くは5割ほど)
- 修正の範囲や回数の制限は(無制限のサービスは少ないため、回数そのものを確認)
- 増刷時の費用(初回より安いかがポイント)
- 契約期間終了後、延長できるか(多くのサービスは有償で延長)
- 配送、断裁、研磨、倉庫保管などの費用は含まれるか(サービスにより様々)
即決をしない
自費出版の契約は即決しないことが大切です。冷静に考えてみると契約内容について問題点が見つかるケースがあります。その場で契約しないで、一度家に持ち帰り、不安な点は周囲の人や専門家などにも相談した上で決めましょう。
他社と比較する
自費出版のサポートを行う業者はたくさんあるため、それぞれの業者を比較することが大切です。サポート内容や料金などを細かく比較してみて、自分の目的に合った業者を探しましょう。それぞれの業者から見積もりをもらい、内容を比較することも重要です。
ただし、各社見積りの内訳が違ったり、付帯するサービスが違ったりするため、並列で比較しづらい場合があります。
その場合、相談しやすい雰囲気の出版社へサービス内容を揃えた見積りをもらうことができないか相談してみましょう。
評判を確認する
事前に出版社の評判について調べておきましょう。過去にトラブルを起こした業者は、悪い評判が広まっている可能性があります。評判を確認して不安を感じる場合は、その業者を利用するのは避けた方が良いでしょう。
細かく打ち合わせをする
自費出版の内容について細かな点を打ち合わせすることは大切です。不明な点をなくし、自分の希望をすべて満たしたサポートを受けられることを目指しましょう。自費出版のそれぞれの過程において、具体的にどんなサポートをしてもらいたいのか希望を伝えておきます。
特に編集工程やデザイン工程は個人の感覚的な面もあるため、「どの程度」をすり合わせることが大切です。
トラブル発生時に返金はある?
事前の契約の内容によってはトラブル時に返金対応を受けられるケースがあります。契約書にキャンセル規定や返金対応に関する記載があれば確認しましょう。
書店への配本部数や書店営業の成果に対し、保証を設けている場合があります。
流通部数が契約書記載の数に達しなかった、書店営業の結果、指定部数の注文が取れなかった場合など、不足分を返金してくれる出版社もあります。
(流通が減ると、配本にかかるコストそのものも少額ですが下がる場合があります。)
返金の仕組みはそれぞれの出版社により異なるため、細かな点を確認しておきましょう。
トラブルによって裁判になった事例もある
自費出版のトラブルで裁判沙汰にまで発展するケースがあります。
たとえば、全国の書店の店頭で販売できると信じ込まされて、多額の出版費用をだまし取られたため訴訟をしたというケースです。自費出版では実際には1冊も店頭に並べられない可能性があるにもかかわらず、このような事実を告げずに契約をさせた点について訴訟が行われました。原告の中には、500部を出版したが、実際に店頭に並んだのは28冊だけというケースがあります。
まとめ
自費出版をする際にさまざまなトラブルに巻き込まれる可能性があります。本記事を参考にして、あらかじめトラブルの事例を知っておきましょう。そして、トラブルを回避しながら自費出版を進めてください。