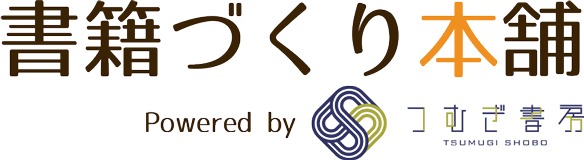本記事では自費出版でエッセイ本を出す際の方法や費用、品質面の注意点、流通させる場合についてを解説します。
エッセイとは
エッセイとは日本語に訳せば散文や随筆のことを指します。形式は自由であり、気軽な形で自分の意見を述べた文章といえます。エッセイの明確な定義は存在しませんが、形式張ったものではなく、日常で感じたことや気持ち、意見などを思うままに書き綴ったものと考えれば良いでしょう。
自費出版に限定せず、出版における「エッセイ」ジャンルの定義も曖昧です。ご自身の作品が厳格にエッセイに属するかは心配する必要はないです。
エッセイを自費出版するメリット
エッセイを自費出版するメリットは、想いをストレートに表現できる点です。読者のウケが良いから、少し奇抜に見えるから等の商業視点で内容を改変する必要がありません。
またご自身の思い出にもなることです。関心が強いテーマや強い意見を持つテーマから、日々思うことや取り留めのない内容までエッセイとして書籍にすることで、思い出や記念の品になるでしょう。
多く売れて、多くの方に読んでもらうことも自由に目指せることが優れた点です。
エッセイを自費出版する方法
知っておくべき1点目は方法です。
大きな流れは原稿を書き、誤字脱字の確認、印刷用データの作成、表紙の作成、印刷製本、販売です。完成した書籍を書店等に並べて販売するか否かで差があります。
ご自身ですべての工程を担えない方が大半かと思います。多くの方は自費出版サービスを提供する出版社を利用します。この場合の方法は、原稿を書く又はライターと相談し原稿を作成する、編集や校閲を依頼する、組版作業と装丁デザイン作業を依頼する、著者校正(印刷前に誤植等がないか確認する作業)をする、印刷製本を依頼、完成書籍を確認する、流通を依頼する、流れです。
大雑把に言えば、原稿を準備した後は、出版社からの確認依頼に応じてチェックし、返答する作業だけです。
出版社に依頼する場合、会社によって対応内容やサービス内容、その料金が異なる点に注意しましょう。事前にしっかりとリサーチした上で業者を選ぶことをおすすめします。
自費出版サービスの資料を無料配布中です。こちらの資料請求ページよりメールでお受け取りください。
自費出版に必要な費用は?
2点目の費用についてです。自費出版サービスを提供する出版社に依頼した場合の費用は、編集校正の程度、本のページ数や紙の種類、製本方法によって大きく異なります。書店でみかける標準的な印刷製本品質を前提にすると、100ページのエッセイ本を100部作るのにかかる費用は約30万円です。高級紙を用いて、カラー印刷ページを含む場合、100ページの本を100部作るのに50万円程度です。
品質を下げる、流通をしない、倉庫保管を頼まず自ら管理することで費用は下げられます。また印刷部数を増やすことで1冊あたり単価は下がります。
多くの方は30~50万円ほどの予算で進めることが多いです。
費用の内訳
細かな点を少し補足します。
自費出版費用の内訳を次にまとめます。
- 編集費、校正費
- 本文レイアウトデザイン費
- 表紙、帯デザイン費
- 印刷費、製本費
- 流通費
- 保管費、事務管理費
ここに含まれない費用には、ゴーストライターに執筆を依頼する場合の費用、挿絵やオリジナルイラストの制作費、しおり制作費、営業費や広告費です。一般的なエッセイの制作では、ご自身で執筆されるケースが多く、オリジナルのしおりを挟むこともなく、新聞広告等を出されることも稀です。多くの方は費用がかからないため、無視しても良いでしょう。
見積もりを取る際のポイント
見積もりの目的は、ご自身が実現したいことの費用を正確に知ることです。後から追加費用が発生するようでは見積もりの目的を果たせません。次の問いにある程度答えられるよう準備ができると良いでしょう。
(出版社の営業や編集者が相談に乗ってくれるケースも多いため、煮詰まった場合には答えが未確定の段階で相談してみることも一つです。)
- 10万~数十万円かけて編集者による編集を希望するか?
- 本文は一般的な作りにするか、雑誌のような複雑な配置を希望するか?
- 挿絵や表紙イラストを希望イメージでオリジナル作成するか?
- 何ページ程度の仕上がりを想定しているか?または完成原稿の文字数は何文字か?
- 印刷用紙にこだわり、高級紙や和紙等を検討しているか?
- 製本はソフトカバーか、ハードカバーか?
- 制作部数は何部か?
- 完成書籍は書店で販売したいか?
- 書店で大きく陳列させたい、POP等とセットで展開させたい、新聞や雑誌等の広告を検討したいか?
何冊から自費出版できる?
3点目は最小部数です。結論、自費出版は1冊から可能です。もちろん、出版社によって対応できる冊数には違いがありますが、多くの業者は1冊からの依頼にも応じてくれます。そのため、試しに1冊作ってみたい方や、思い出や記念として1冊だけ出版したい方に対応しています。1冊のみの依頼であれば印刷費用は最小限に抑えられますが、編集やデザイン費用は下がらないため、想像よりも高いケースが多いでしょう。
(1冊作る場合も10~20万円ほどかかり、10冊作る場合との費用差分はほぼありません。)
文章を書くのが苦手でも大丈夫?
4点目は執筆に不安がある場合の対処です。自費出版のサービスは単に書籍の印刷をするだけではなく、編集や校正のサービスも含まれています。(含まれていないサービスや編集の程度が選べるサービスもあります。)実際に商業出版を扱っているプロの編集者からサポートを受けられるサービスもあります。
出版社によっては、プロのライターを用意して、取材をした上で代わりに文章化してくれるサービスもあります。ご自身で文章を書くことが苦手な方はライティングや編集サービスを中心に据えて依頼先を考えると良いでしょう。
エッセイを本屋に並べることはできる?
5点目は流通についてです。自費出版で作ったエッセイ本を本屋に並べることができるのか解説します。結論は大半の出版社で書店配本できますが、注意点もあるため以下から見ていきましょう。
本屋に並べるには
本屋に配本し並べてもらうにはISBNコードとJANコードが必要です。ISBNコードとは書籍の識別番号であり、JANコードは書籍のカテゴリや価格等の情報を含めたバーコードのことです。2つのコードを取得することで書店への流通が可能になります。大半の出版社はコード発行に対応しています。
個人での取得もできないことはないですが、費用面や申請作業面であまりおすすめしません。(年に数十タイトルの自費出版を行う予定であれば、ご自身でISBNコードの取得を検討しても良いと思います。)
電子出版も可能?
自費出版本を電子出版することも可能です。電子出版するためには、電子書籍のデータを用意する必要があります。データさえあれば、電子書籍を販売するサービスに登録をして、ファイルを送信し、審査を受けて内容に問題がなければ販売できます。
出版社の中には自費出版のサービスとして電子出版に対応しているケースがあります。この場合は、原稿のデータさえ渡せば、電子書籍サイトでの販売まですべてを任せられるため便利です。
電子出版の場合は印刷をする工程がなく費用も安価なため、赤字になりにくい点が魅力といえます。全国各地の人達を対象にエッセイを販売できる点も魅力です。
希望通り本屋に配本される?売れる?
希望冊数次第では希望通りに配本できない場合があります。具体的には1万冊を配本したいケースです。9割方で希望数を配本することはできないでしょう。
書店数は1万店をきったといわれる昨今(調査もとにより、ぎりぎり1万店のデータもあります。)、その中でもある程度規模の大きい書店でないと知名度のない著者の書籍は配本を受けてもらえないでしょう。
理由は中型店や小型店(売り場300坪以下)の陳列スペースにあります。小規模な店舗では当然に陳列可能な冊数も限定的であるため、人気作品の陳列に限られます。
私の本1冊くらいなら、、、と思う気持ちがわきそうですが、年間約7万タイトルが発売される日本では、まさにこの「私の本1冊くらいなら」と思っている著者が多くいることでしょう。
ただし、特殊な職業に就いている方や特殊な経験をもとに作られたエッセイなどカラーの濃い作品に需要はあります。エッセイ本として多くの人が手に取りたくなるようなアピールポイントを作ることが大切です。
よくある疑問に1門1答形式で
おおよそエッセイの主要な情報はまとめてきました。追加で質問いただくことの多い内容をまとめておきます。
依頼する出版社の選び方は?
まずはご自身の予算を確認しましょう。100万円以下の予算であれば(多くの方は数十万円の予算かと思います。)安価な価格帯で出版サービスを提供する数社に相談見ると良いでしょう。当社も安価な出版社の一つです。
100万円以上の予算であれば、こだわりたいポイントを整理しましょう。多くの場合で編集にお金をかけるか、印刷部数が多いかのどちらかが前提にあると思います。
部数が多く、販売を考えている場合には、書店営業や広告に対応する出版社を選びます。同じ内容であっても出版社により金額差が非常に大きいため、相見積もりを取ることが重要です。
契約で注意すべきことは?
通常の自費出版は、完成した書籍の所有者が依頼者(著者)になります。
稀に出版社に所有権が設定される契約や、売上に対する分配割合(印税)が極端に低い契約があります。分配割合は依頼者の取り分30~50%ほどが目安です。
理解し納得した上での契約であれば問題ないですが、知らぬままにならないよう注意しましょう。
著作権等の権利は?
著作権は著者のものです。出版権は出版する以上は出版社に設定するものです。
著作権が出版社等の他社に設定されることはないはずですが、契約時は注意しましょう。出版権は出版するものに著作権者が付与する権利するです。出版社は出版権がなければ出版を代行することができません。ただし、自費出版では出版後に出版権を解除することができるか、(依頼者にとって自由度があるか)を確認しておくと良いでしょう。
印税は?
前の項でも少し触れていますが、エッセイの自費出版をし、その売上代金から著者に支払うお金は「売上分配金」と呼ばれます。
印税とは、著作権使用料の別称で、その名の通り原稿を使わせてももらうことへの対価です。自費出版は著者自身が著作物を作るため、使用料には該当せず、売上金の一部を受け取ることから「売上分配金」と呼ばれます。
書籍の売上のうち、30%~50%程度を著者が受け取ることが平均的です。
まとめ
自費出版でエッセイ本を出すことは可能です。出版社などが提供する自費出版サービスを上手に利用しましょう。このブログを運営する「書籍づくり本舗」もエッセイの出版に対応しています。ぜひサイト内を見ていってください。