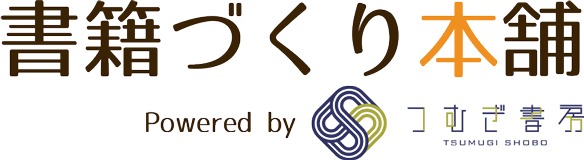自費出版では書籍用紙を選べる出版社が多いです。用紙の種類は多く、選び方が分からない方も多いでしょう。本記事では用紙の種類、選び方などを解説します。
自費出版の用紙の種類
出版で利用できる用紙について、種類や特徴をそれぞれ紹介します。一般的には商業出版と自費出版で使用可能な用紙に違いはありません。
上質紙
上質紙は非常にメジャーな用紙で価格も安価です。光沢のない白色紙であり、ご自宅のプリンター用紙としてもよく使われています。化学パルプの配合割合が100%でコピー用紙の中でも特に白く見えるものが上質紙です。書籍では本文の印刷で使われます。カラー印刷やベタ塗りと相性が悪く、写真集やイラスト集には不向きです。
コート紙
コート紙はカラー印刷に向いている用紙です。紙の表面にコート剤を塗ったもので、そのため光沢のあり、色を鮮やかに再現できます。コート剤を塗ることから塗工紙と呼ばれる種類に該当します。身近なものでは折込チラシなどでよく選ばれる用紙で、価格は安価で上質紙とほぼ変わりません。本文でカラーをふんだんに利用する場合はコート紙を選びましょう。
アート紙
アート紙は光沢があり、この光沢はコート紙よりも強いです。コート紙と同様に塗工紙の一種で、上質紙の表面に液剤を塗ったものです。コート紙よりも厚く塗るため、表面はより滑らかになります。価格はその分高いです。鮮やかな印刷が可能であり、カラー印刷に適しています。
マット紙(マットコート紙)
マット紙は光沢がない(つや消しされている)用紙です。他の用紙と同様に紙の表面を塗りますが、この塗工剤にマットなものを使用します。
マット紙とマットコート紙はほぼ同義として扱われ、製紙メーカーにより呼び名が異なる程度と認識すると良いでしょう。落ち着きのある印刷面にしたい場合や、鉛筆等での書き込みを想定した書籍(漢字ドリルなど)で採用を検討するのが良いでしょう。
価格はコート紙よりもやや高いです。
アートポスト
アートポストは厚手で光沢のある用紙です。発色が良いため、表紙用紙として使用されます。コート紙を厚くした用紙であるため、価格はコート紙よりも高くなります。身近なものではポストカードや名刺で多く利用されています。
書籍用紙
書籍用紙とは書籍の本文に使われることが多い用紙です。書籍でクリーム色の用紙を見たことがあれば、恐らくそれは書籍用紙です。メーカーにより個別の名称が異なり、クリームキンマリや琥珀と呼ばれることも多いです。
コート紙と比較し、発色が落ちるためカラー印刷には不向きです。目が疲れにくく、インクの定着が良いため、小説や自伝など文章中心の書籍におすすめできます。書籍用紙は上質紙よりも少し高いです。
ラフクリーム琥珀
ラフクリーム琥珀はクリーム色をした本文用紙です。上質紙をベースとしており、退色しにくく保存性に優れています。前述の書籍用紙とほぼ同じ性質です。
書籍用紙との違いはやや厚みがあるため、嵩が出る点です。(同じページ数で印刷した際、ラフクリーム琥珀を用いると書籍が分厚くなります。)
ホワイトコハクライト
ホワイトコハクライトは上質紙より多少厚みがあり軽いのが特徴の用紙です。ラフクリーム琥珀と同様に嵩が出る用紙です。自然な白色で、書籍や冊子などの本文用紙として幅広く用いられます。メジャーな用紙でしたが、日本製紙が生産を終了したため、今後は販売がほぼなくなる予定です。
モンテシオン
モンテシオンは日本製紙の石巻工場で生産される用紙で、ラフな質感が特徴の本文用紙です。嵩高用紙の中でも非常に厚みのある用紙で、イラスト集での使用と相性が良いです。ただし、長期保管との相性があまり良くなく、時間経過により黄色みがかった用紙になる点は注意が必要です。高級紙ではなく、標準的な価格の用紙です。
色上質紙
色上質紙は上質紙に色をつけたものです。上質紙をベースとしているため、光沢がなく手触りがさらりとしている点は共通しています。豊富なカラーバリエーションがあり、表紙や目次などによく使われます。
レザック66
レザック66は1966年に発売されたためレザック66と呼ばれています。レザー(仔牛の革)をイメージさせる用紙です。カラーバリエーションは豊富で、学級文集やパンフレットの用紙によく利用されます。温かみと高級感を感じさせるのが特徴です。
サンマット
サンマットはマットコート用紙(光沢のないアートポスト紙)の中で、最も厚みのある用紙です。自然な風合いの白で、落ち着いた印象を与えます。高級印刷用紙とされていて、費用は高いです。強度もあることから長期保管を叶えたい書籍の表紙に適しています。
用紙の選び方
自費出版の用紙選びに際し、目的別のおすすめ用紙を紹介します。
表紙におすすめな用紙
表紙におすすめな用紙は以下の通りです。
- アートポスト
- サンマット
- レザック66
一般的な並製本(本屋に並ぶ標準的な書籍の装丁)であれば、アートポストで間違いないでしょう。コストは気にせず、長期保管したい(100年、200年と保管したい)場合にはサンマットが適しています。
地域の史料など、派手さを抑えて品のあつ仕上がりを重視される場合には、レザックを検討すると良いでしょう。
カバーをかける場合には、表紙の用紙はコストを抑える目的でもアートポストに軍配です。
本文におすすめな用紙
本文用紙は、書籍のジャンルに応じて考えると良いでしょう。
小説など文字中心の書籍
- 書籍用紙
- ラフクリーム琥珀
眼への負担が少ないクリーム系の用紙で、読者の読みやすさを意識するとこの2種ではないでしょうか。こだわりに応じて特殊な用紙を選ぶ手もありますが、昨今の紙不足もあり、用紙の確保に時間を要し、制作期間が伸びる可能性もあるため、通常はメジャーな書籍用紙が良いでしょう。
コミックなどのイラスト中心の書籍
- モンテシオン
- 上質紙
細かな線の再現性、にじみにくさからモンテシオンが良いでしょう。軽くてざらっとした触り心地が読みやすさにおいてもプラスです。
他にもここでは紹介しなかったコミック紙を用いることも一つです。ただし、コミック紙は流通が特殊なため、一般論として紹介することが難しいため、(印刷所により仕入れているコミック紙は異なる場合が多いため)割愛します。
写真集などのフルカラー印刷の書籍
- コート紙
- マットコート紙
基本はコート紙で、光沢の有無から選択することが良いでしょう。写真点数が少ない場合には、用紙の厚み(嵩)を調整すると希望に近い形になります。
一般的な価格での販売には難しい面もありますが、(コストがかかりすぎる点で)ラスターペーパーを選択することも一つです。
(写真家の方はご存知かと思いますラスタープリントのラスターです。)
絵本などのフルカラー印刷の書籍
- コート紙
多くの絵本では、コート紙を採用します。非常に分厚いページ作りとしたい場合には、厚紙やボール紙を挟むなどの処理で厚みを出します。画用紙のような質感を出したい場合には、本記事では詳細を触れていませんが、サンシオンホワイトという用紙も良いでしょう。
用紙選びの注意点
用紙選びに失敗しないための注意点、コツを紹介します。
実物を見て選ぶ
実際に用紙の見本を見ながら選ぶことは一つです。実物を触る、見ることでイメージしやすくなるからです。ここでご紹介した用紙の大半は、用紙見本として多くの場所で売られているものです。数百円程度で手に入れることができます。理想とする本のイメージに最適な用紙を探すと良いです。
編集者の意見を参考にする
出版社に依頼をして自費出版を進める場合、用紙のイメージを編集者に伝えることで意見をもらえます。編集者からある程度用紙を紹介してもらえるため、その中から選ぶと失敗しないでしょう。
また、用紙にはジャンルごとに基本的な組み合わせが存在するため、それでお願いするという方法もあります。
ご自身の本棚から希望に近い書籍を決める
出版を検討中の方であれば、多くは読書家でもあるでしょう。ご自身の蔵書からカバー、表紙、見返し、本文用紙で良いと思うものを見つけましょう。
出版社や印刷所に該当書籍を預け、近い用紙を選定してもらうことも一つです。(廃番・廃品になった用紙も多くあるため、古い書籍と同一用紙を用いることが現実的ではない場合もあります。)
まとめ
自費出版する際に用紙選びは重要なポイントです。多くの用紙が存在しているため、種類の違いを理解して、イメージに合った用紙を選びましょう。